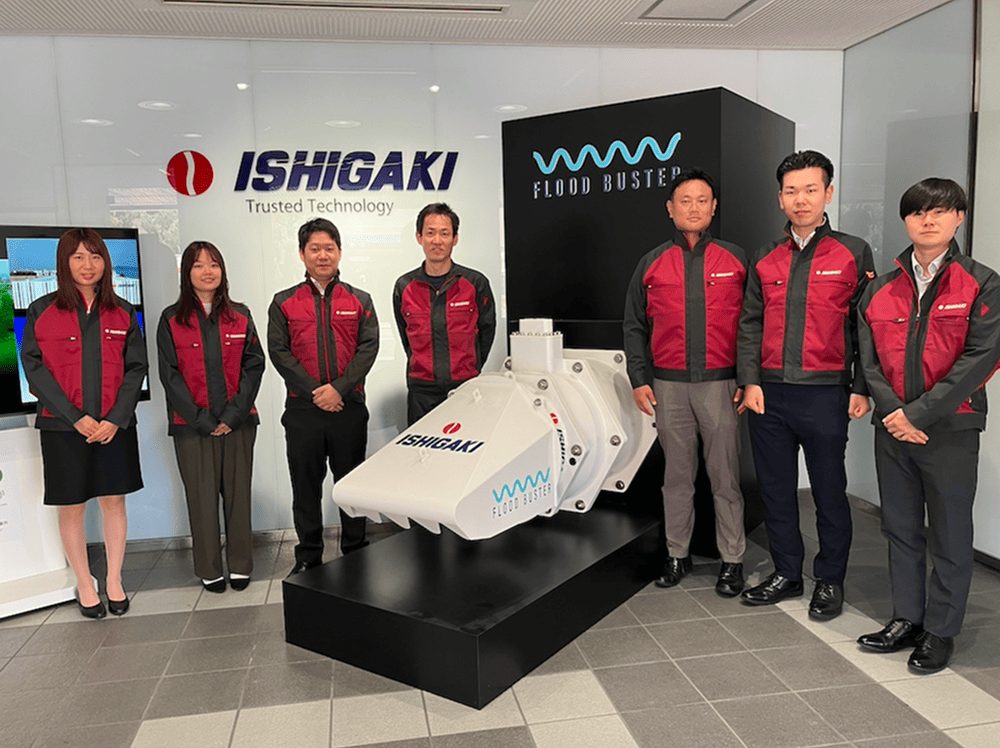はじめに、私どもとのなれそめについてお聞かせください。
もともと保守部門で使っていた地図の使い勝手に大きな課題を感じていました。そこで、展示会に行った際に地図サービスの情報収集を兼ねて色々なセミナーに参加しました。私自身、開発もするので技術力があって、かつ、フットワークが軽い会社があったらいいなと思っていたのです。加えてカジュアルに接することができれば、なおいいだろうと思っていたところでゴーガさんと出会いました。一度アポイントをとってみたらウェブ会議ですぐにお話しでき、普段使い慣れている Google のソリューション( G Suite やハングアウト)をゴーガさんでも取り入れているという点に親近感が湧きました。先ほど挙げたポイントにピタリとはまる人たちだと感じました。
ありがとうございます。出会った当時のことをもう少し詳しく伺いたいのですが、どのような点に課題を感じていらっしゃったのですか。
その頃使っていた地図は、PCでしか使うことができないものでした。外出の場合は地図を印刷しなくてはいけなかったですし、拡大や縮小もできず、さらには情報の陳腐化という点も問題に感じていました。
その際、他の地図サービスはご検討しましたか。
国内外様々な地図サービスをリストアップしていました。やはり Google Maps Platform はストリートビューなどの機能が充実していますし、グローバルで使えるという点も優れていると感じました。グローバルでの表示はまだまだ模索中ですが、将来的には地図一つで全世界の物件を表示できるとよいと考えています。

FUJITECにおける部門をまたいだ"All on Map"概念図

セーフネットセンターの様子。スクリーンに映った地図上で地震発生時の復旧状況を共有(※画像を加工しています)
保守の方は一日あたり何件まわるのですか。
定期点検の場合は数件ですが、地震災害時は100台以上停止することもあります。復旧を急ぐため、スマートフォンで周りの停止物件を確認しながら、近くて病院など優先順位の高い順に、手分けして復旧していきます。
想像以上にたくさんまわるのですね。そういう場合、ルートは重要になってきますか。
そうです。フィールド向けのサービスとしてAIで出向者を手配し、そのサービスと Google Maps Platform を連携し、ディープラーニングでより効率的にまわることができるルートを示す、などといったことが今後はできるようにしていくつもりです。以前は保守現場にも、地図以外にノートPCを持っていかないと必要な情報にアクセスすることができないため、緊急時でも何かと手間が発生していました。しかし、 Google Maps Platform を導入してからはスマートフォンでアクセスできますのでそうした無駄な手間を削減できるようになりました。情報の可視化や収集は現場でもセンターでもスムーズに行なえるようになっていますので、これからは収集した情報とその有効活用を課題として取り組んでいく予定です。